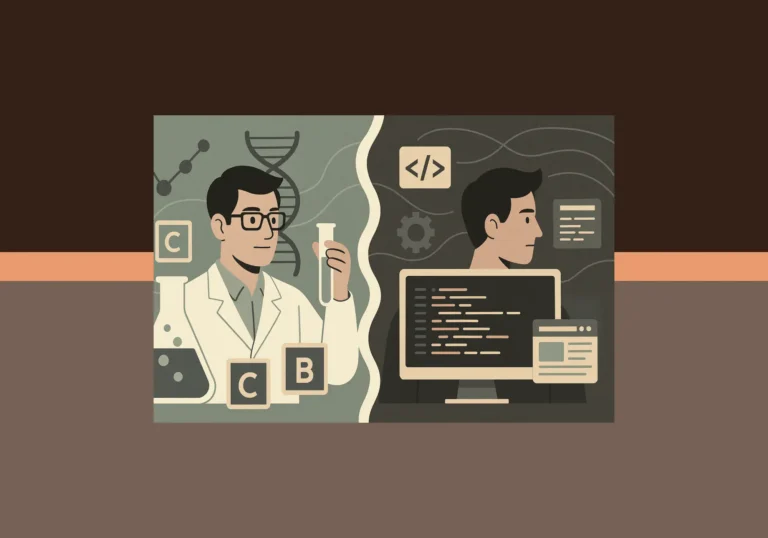
化学者からWebエンジニアへ転身して気づいた、意外な共通点
この記事のまとめ
- ⚡東京工業大学(現:東京科学大学)で化学を学び、大手化学メーカーで7年働いた筆者がWeb業界へ転身
- ⚡HSPの特性に気づき、自分らしい働き方を模索した結果の決断
- ⚡化学研究の「仮説検証」「データ分析」「品質管理」の考え方がWeb開発に驚くほど活きている
- ⚡一見違う分野でも、根底にある「課題解決への情熱」は共通している
元化学者のWebエンジニアです、と自己紹介すると、たいてい「え?」という顔をされます。
東京工業大学(現:東京科学大学)で6年間、触媒化学とバイオマスの研究に没頭し、新卒で入った大手化学メーカーでは7年間、白衣を着て実験室にこもっていました。そんな私が今、パソコンに向かってコードを書いているなんて、自分でも時々不思議に思います。
でも実際にやってみると、化学とWebって、思っていたより共通点が多いんです。
きっかけは、自分の「生きづらさ」と向き合ったこと
化学メーカーでの仕事は充実していました。プロジェクトリーダーとして後輩を指導したり、新しい材料開発に携わったり。会社での立場も安定してきていました。
ただ、なんというか、息苦しかったんです。
大企業特有の縦割り文化、変化を嫌う体質、そして何より、周りの目を気にしすぎる自分自身。あるとき、自分がHSP(Highly Sensitive Person)だと知って、今までの生きづらさの理由が腑に落ちました。人の感情に敏感すぎて疲れてしまうこと、自己表現が苦手なこと、全部つながっていたんです。
そんなとき、大学時代の友人から突然の誘いが。
「Web系の会社を一緒にやらないか」
全く未経験の分野でしたが、「人に寄り添う仕事がしたい」「より直接的にクライアントの課題解決に関わりたい」という思いから、思い切って飛び込むことにしたのです。
それに、肌が弱くて化学物質を扱うたびにヒヤヒヤしていた私にとって、パソコン一台で仕事ができる環境は正直ありがたかった(笑)。
フラスコからブラウザへ – 化学者の習慣が意外と役立つ
転職して最初の数ヶ月は、正直きつかったです。HTMLって何?CSSって?状態からのスタートでしたから。
でも、あるとき気づいたんです。Web開発やWeb制作って、化学実験とすごく似ているということに。
仮説を立てて、実験して、また仮説を立てる
たとえば先日、あるECサイトの売上改善を担当しました。「商品画像を大きくしたら購買意欲が上がるんじゃないか」と考えて、まずはテスト。結果は面白いことに、パソコンでは売上が15%アップしたのに、スマホでは逆に3%ダウン。
昔の研究者魂がうずいて、なぜそうなったのか検証。画像の読み込み速度、ユーザーのスクロール行動、デバイスごとの画面サイズ…。結局、スマホでは画像が大きすぎて、価格や購入ボタンが画面外に押し出されていたことが原因でした。
こういう「仮説→検証→分析→新たな仮説」のサイクルって、まさに研究室でやっていたことそのもの。フラスコがブラウザに変わっただけで、根本的な思考プロセスは同じなんです。
データを多角的に見る癖が染みついている
化学分析では、一つの物質をGC-MSで調べて、NMRで確認して、IRでも測定して、…と、いろんな角度からデータを取ります。一つの手法だけじゃ見落としがあるかもしれないから。
この習慣、Web解析でめちゃくちゃ役立ってます。
「お問い合わせが減った」という相談を受けたとき、普通はアクセス数を確認して終わりかもしれません。でも私は、検索順位、ユーザーの行動パターン、フォームの完了率、競合の動向まで、とにかくあらゆるデータを集めます。実際、あるケースでは、アクセス数は問題なかったのに、システムアップデート後に特定のブラウザでフォームがエラーを起こしていたことが判明。データを多角的に見る習慣があったからこそ、本当の原因にたどり着けました。
「なんとなく」では済まされない世界で鍛えられた説明力
研究発表では、教授から「なぜそう言えるの?」「根拠は?」と鋭く突っ込まれまくります。論文を書くときも、すべての主張に根拠が必要。この訓練のおかげで、クライアントへの提案も自然と根拠ベースになりました。
「このデザインがいいと思います」じゃなくて、「ヒートマップ分析の結果、ユーザーの70%がこのエリアに注目しているので、ここに重要な情報を配置することで、コンバージョン率の向上が期待できます」みたいな説明ができる。
あるクライアントさんに「他の制作会社と違って、なぜそうするのかがはっきりしていて安心」と言われたときは、研究者時代の苦労が報われた気がしました。
HSPだからこそできること
転職の大きな理由だったHSPという特性。実はこれ、Web業界では強みになっています。
クライアントの言葉の裏にある本音を感じ取れたり、ユーザーがどこで迷うか直感的にわかったり。「共感力が高い」って、ユーザー目線でものを作るときには最高の武器なんです。
以前、あるクライアントさんが「うちのサイト、なんか違うんだよね…」とモヤモヤされていました。具体的に何が問題か言語化できない様子。でも、話を聞いているうちに、「ブランドイメージと実際のサイトの雰囲気がズレている」ことが本質的な悩みだと感じ取れました。結果、ロゴやカラーはそのままに、フォントと余白、写真のトーンを調整することで、「これこれ!」と喜んでいただけました。
違う分野に見えて、実は同じことをしている
化学研究もWeb開発も、結局は「誰かの困りごとを解決する」仕事です。
化学は、環境問題やエネルギー問題を分子レベルから解決しようとする。Webは、ビジネスの課題をデジタル技術で解決しようとする。手段は違えど、目指すところは同じ。
違いがあるとすれば、結果が見えるまでのスピード感。化学の研究成果が製品になるまで10年以上かかることもあるけど、Webなら最短数週間で「売上が上がった!」「お問い合わせが増えた!」という声が聞ける。この即効性は、正直やみつきになります。
これから目指したいこと
「共感力で化学反応を起こすWebクリエイター」
ちょっとクサいキャッチコピーですが(笑)、これが今の私の目標です。
化学者時代に培った論理的思考と、HSPとしての共感力。この組み合わせで、ただ見た目がきれいなサイトじゃなくて、本当に成果につながるサイトを作っていきたい。
最近は、同じHSPの方や、肌トラブルで悩む方、子育てに悩むパパ・ママ向けのサービス開発も考えています。自分が経験した「生きづらさ」を、誰かの「生きやすさ」に変えられたらいいなと。
化学からWebへ。一見すると大きな方向転換に見えるかもしれません。でも私にとっては、「課題解決への情熱」という軸は変わらないまま、表現方法を変えただけ。フラスコをパソコンに持ち替えて、今日も誰かの課題と向き合っています。
もし「うちのサイト、なんとかしたいんだけど…」というお悩みがあれば、ぜひお声がけください。元化学者ならではの視点で、あなたのビジネスに化学反応を起こすお手伝いをさせていただきます。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にこちらからお声がけください!
